
ノズルやハウジングのポートがちょっとカッコいいっす。
Atomic Floyd / TwistJax AcousticSteel の
左右チャンネルのバラつきを調べてみるの巻
(2009/11/29)

ノズルやハウジングのポートがちょっとカッコいいっす。
左右チャンネルの件の前に、なげやりな文を書きまして感想はサッサと終了。
| 【なげやり俺感想】 外観・作り: ステンレス製のソリッド外観はなかなかカッコよい。 ノズル部分が1/3回転程回る機構も滑らかで良好。 (ハウジングの形が殆ど同じに見えるHiDefJaxでは、ノズルは固定されている様子。ま、あちらはシャフトがないんで動く必要ないですし。) 装着感: 片chで約8.5g。一般的なカナル型イヤホンが概ね3g程度(※1)であることからすると2〜3倍の重さ。 耳へのフィット感は良いし、密閉度も比較的保ちやすいのでズレにくいとは思うけれど、それなりに重い感じあり。 イヤホンを出したりしまう際に、左右のハウジングがアメリカンクラッカーのようにカチンカチンとぶつかりがちなのが少し気恥ずかしい。 布製のケーブル被覆は取り回しは良い。しかしながら、首を動かすと衣服とこすれてゴワゴワと音がしやすいので、自分は正直あまり好きではない。 (※1)俺実測でaudio-techinca ATH-CKS70:3.4g、 ATH-CK90PRO:2.0g、 Bose IE:4.2g、 Roland RH-PM5:2.3g 音: 全体:ドンシャリ。ダイナミック型のイヤホンらしくどちらかといえば派手目で、脚色した音で楽しませようとするタイプと思われ。 低音・高音の増強具合は長時間のリスニングで許容できるギリギリの線と感じた。チューニングはなかなか煮詰められている印象。 どちらかと言えば、ポップス、ロック向きの様子。クラシックも悪くはないが、大編成のオーケストラでは低音が少しだけモコモコした残響の多いホールで聞いているような印象あり。 低域:20Hz程度のローエンドまで伸びは十分。量感は多くキックやベース派手でウルサく感じる音源の割合はそれなりに多いと感じる。 歪み感の低さ/制動感といった質についてはダイナミック型としては比較的良好な部類だと思う。 中域:ボーカルは楽器に比べわずかに引いた印象でどちらかといえば地味。全体としてさほど不自然さはないけれど、サ行のキツさはそれなりに強い。 低音の強さとあいまってあまりお上品とは言えないがギリギリ許容できる範囲のように感じた。 高域:バイオリンはほんのわずかにヌケと立体感が悪いように感じること以外は、イヤホンとしてはそれなりに自然に聴こえるように思う。 (ヌケと立体感がいまひとつな原因は、おそらく8kHzあたりの音圧が相対的に低いためと推測します。) アコースティックギターは少し野太く感じる場面が多いけれど、鮮度は良好。 トランペットほんのわずかに地味でヌケが悪いような印象はあるが、不自然とまでは言えず普通に楽しめる範疇。 ハイハットやシンバルはよく目立ち、解像感は良い部類だと思うが、アタック時に派手すぎてノッペリとした印象となる場面があるように感じる点は惜しい。 その他: どちらかといえば音量が取りにくい部類かと。iPodでボリューム60%程度、sonyのX1060で20強/30の位置で使うことが多いです。 俺総合: 自分としては、このくらいまでのドンシャリなら十分アリ。 でも・・・おそらく元気な時しか使わない感もあり。そしてこれよりドンシャリ傾向が強いとたぶんダメ。 BA型に比べれば、荒っぽいとも感じるドンシャリっぷりと感じました。ご自分の許容限界を超えていないか要確認と思われ。 |
ドライバーの特性を調べるには、まずはT/Sパラメータを見ておくのが(たぶん)定石ですから、
まずはインピーダンスから左右の違いを見てみましょ〜。
【グラフ1】Impedance(非装着時)
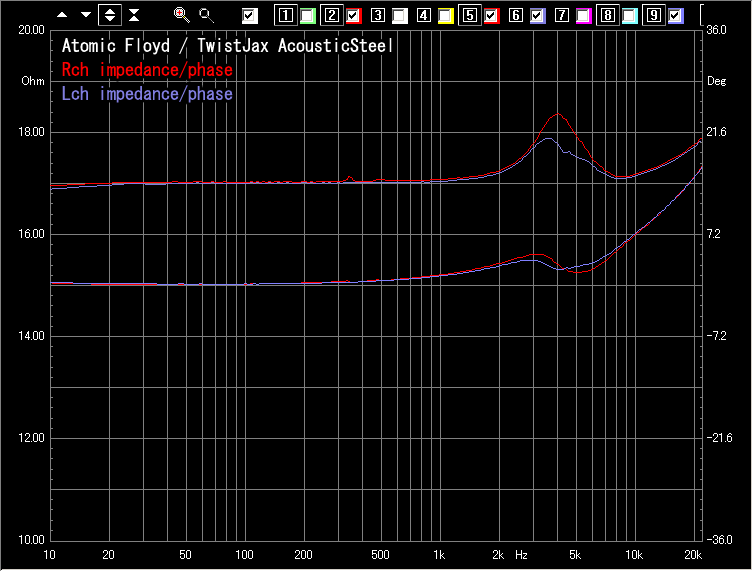
うーん。かなり違いますね。
上記【グラフ1】インピーダンス特性から計算したT/Sパラメータの一部
| Lch | Rch |
| Fs 3556.7680 Hz Qts 0.6570 Zmax 17.8918 Ω |
Fs 3967.1540 Hz Qts 0.9875 Zmax 18.3672 Ω |
左右のユニットでそれなりに最低共振周波数(Fs)、共振の鋭さQ値(Qts)など、インピーダンス特性にそれなりの違いがあります。
もちろんこの機種がおかしいワケではなく、このくらいの左右の違いは、どのヘッドホンでもフツーです。
(MDR-CD900STの例はココ)
上の結果によりまして、いろいろと憶測をしてみるわけです。
| <左右のインピーダンスの違いから音圧の特性の問題点を予想ってか憶測してみる> ①音圧が最大となる最低共振周波数が左右chで400Hzほど違っている。(なのでこのあたりの定位は僅かに乱れるのかな?) ②Rchの方が少しダンプが甘そう。(RchのFs付近の音圧が少し高くなり、これまた定位がわずかに乱れるのかしらん?) ③340Hzあたりに、Rchだけに存在する小さな乱れがある。(これは何で起きているんでせう?理由はわかりませぬがF特や過渡応答を悪くしそうな予感。) ・・・など。 |
【グラフ2】FR(L/Rch)
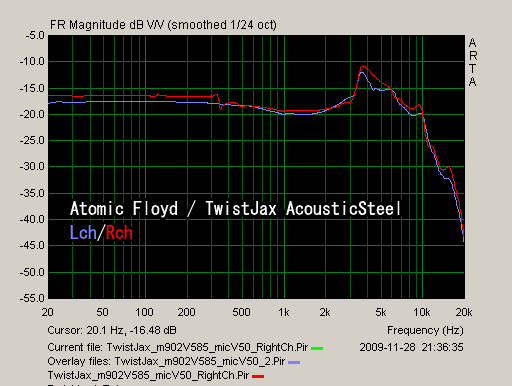
①のいきなり予想ハズレ〜orz。最低共振周波数の違いは、装着すると殆ど同じになっている様子。
②は予想どおり、Rchの方がFs(4kHz弱)の音圧が高い。・・・つーても2dB位の差だし気にしないし、普通わかんないし問題なし。
③はちょっと予想を超えるくらいに影響が出ている様子。Rchだけ340Hz近辺に乱れが音圧に反映されちゃってますね。・・・き・・気にしないぞ。
【グラフ3】位相(L/Rch) ※200Hz〜6kHz
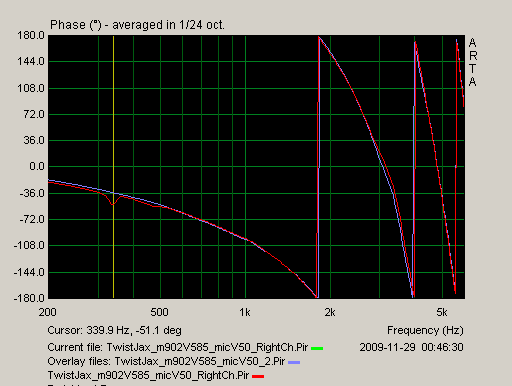
340Hzの位相の乱れはこんな感じ。
「10度強くらいの乱れだし大したことないじゃん?」というのは、以下の群遅延の【グラフ4】見ると分かるようにマチガイのようです。
【グラフ4】群遅延:位相を周波数で微分したもの(L/Rch) ※100Hz〜10kHz
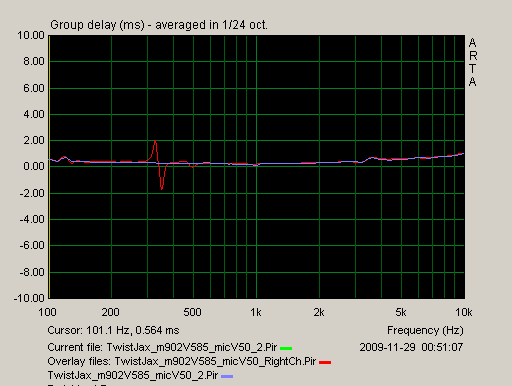
±2msecくらい群遅延時間に乱れが出る様子。
・・・えーと340Hzだと1周期で2.94msec。±1.5周期分に相当する(マチガイ。±0.68周期に相当する、です。)・・・ってなんかすごい乱れている気がします。
でも局所的だし、これくらいだと普通に音楽を聴いている分にはわかんないのかな?・・・微妙なところです。
【グラフ5】CSD
| Lch | Rch |
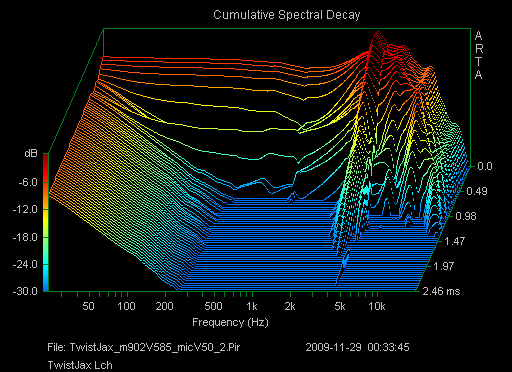 |
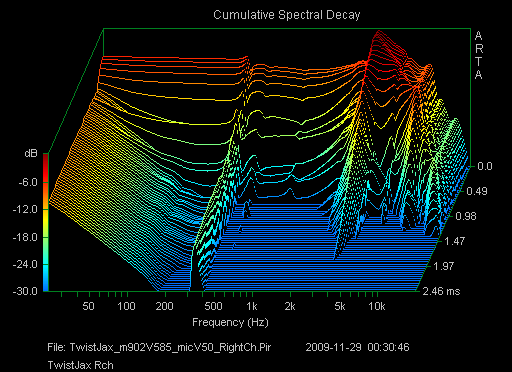 |
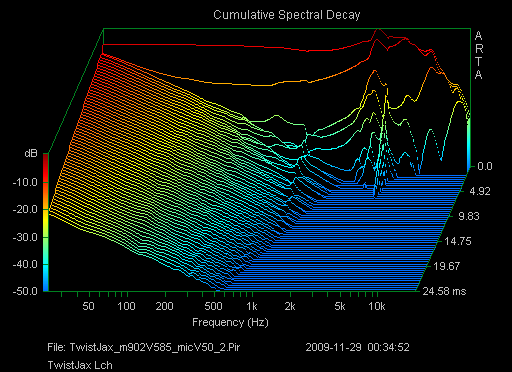 |
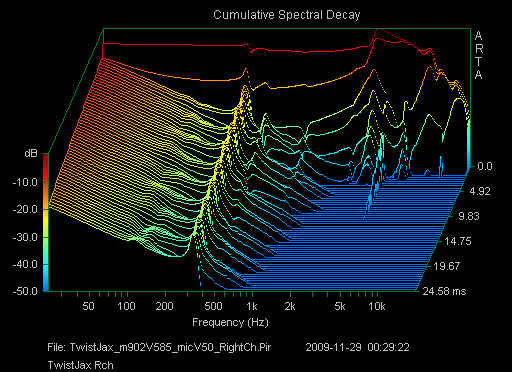 |
340Hzの乱れはCSDでもなかなか強烈に表れており、減衰せず長時間残存している様子。
分割振動でしょうかね、こりゃ。
【グラフ6】三角波再生
タワムレに340Hzの三角波を再生して、波形の崩れ具合を見てみました。
矩形波の観測でも良いかと思われますが、もー少しマイルドに現実的な感じで三角波かな・・・といった程度の理由です。
矩形波はうるさ過ぎてカンに触るからヤだ、ってのもありますが。
| Lch (340Hz三角波再生) | Rch (340Hz三角波再生) |
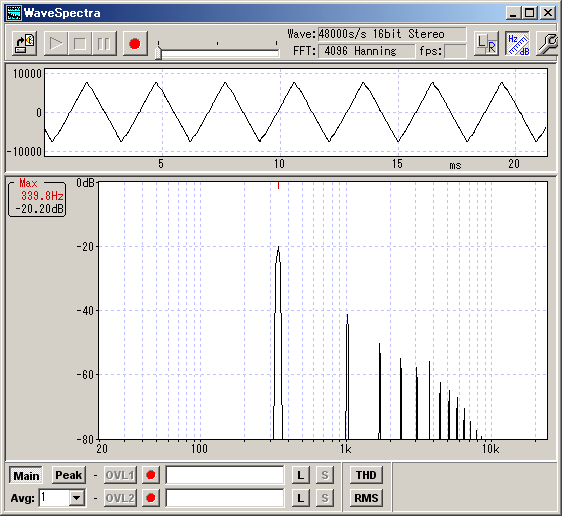 |
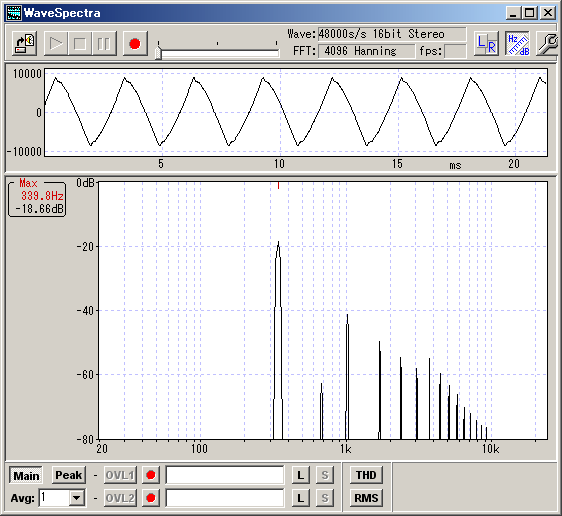 |
本来三角波であれば奇数次倍音しか出ないはずです。(ここでは340Hzの基本波なので、1020Hz、1700Hz、2380Hz・・・)
Lchはそのとおりになっていますけれど、Rchは680Hzの偶数次倍音が生じており、波形は見た目でも明らかに非対称になってますね。
俺聴覚上もそれなりに歪んだ音に聴こえます。
自分は、普通に音楽を聴いているくらいでは違和感は感じませんが、両chにサイン波や三角波など全く同じ信号を入れてゆっくりスイープすると、340Hz近辺では定位がフラフラしてフランジャーをかけたように不安定な印象になりますし、付帯音の如き歪みを感じますので、音源や人によっては違和感を感じる場面もありうるやもしれませぬ。
=====================================================
以上、長々と左右chの特性の違いを見てまいりましたが、
結局のところ、大量のドライバーのインピーダンスを測ってT/Sパラメータやグリッチの状況によって選抜して左右のマッチングを取る、なんてことをメーカーでしない限りは
この位の相違は普通のヘッドホン/イヤホンにはあるのでしょう。
|
【今回の俺結論】 |