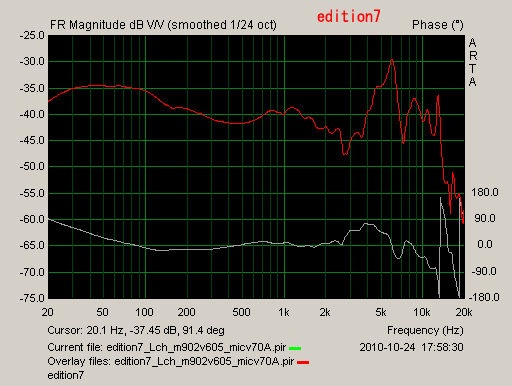Ultrasone edition10
(2010/10/23新規作成)
【グラフ1】周波数特性(edition10 vs. edition8)
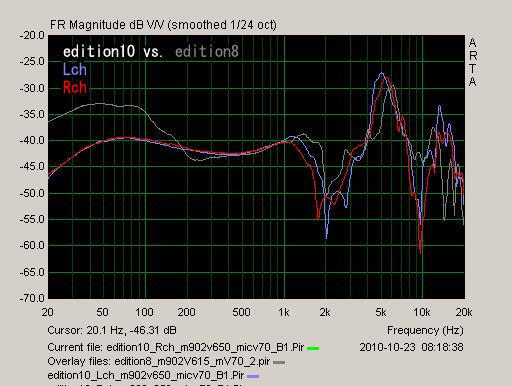
editionシリーズ(?)は、いずれの機種も周波数特性の特徴に類似性が相当高い印象あり。
(具体的には2kHz強のディップや、5〜6kHzあたりの大きなピークという特徴)
ediion10は開放型であるため、
100Hz以下の低音の音圧は、edition8と比較して6dB程度大人しく、
かつ、50Hz以下のローエンドは開放型らしくダラ下がり、という違いはあります。
しかしそれにしても、開放型にしてはかなりのクセの強い周波数特性とお見受けします。
【グラフ2】インピーダンス(開放時と装着時の変化をGIFアニメにしてみますた。意味あんのかと。)
開放型とはいえ、装着時の空気によるダンピングはそれなりにある、という事が分かるかと思います。
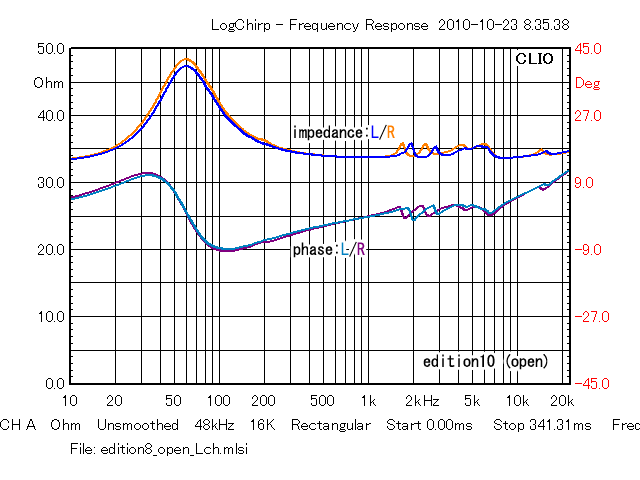
最低共振周波数は60Hz、Qts=0.6程度の様子(非装着時)。
(※Qtsはユニットの機械系+電気系トータルでの共振の鋭さをあらわします。Qtsの値が大きいほど強く共振して振動が収まりにくい=制動が効いていないことをあらわします。)
低音のダンピングについて、
密閉型のedition8は非装着時でQts=0.35程度と強くダンピングされていたのに比べれば、
ediion10は当然ながらダンピングは緩いです。(・・・っていうか、そうしませんと開放型では低音が出なくなっちゃいますし。)
とはいえ装着時でQts=0.50〜0.55程度と、臨界制動条件Qts=0.5近くなので(設計で狙ってるのかは不明)、
一概にedition10の過渡特性が悪い、とも言えないような気もしますが・・・ゴニョゴニョ・・・
えーと・・・ちゃんとステップ応答やらインパルス応答やらの過渡応答の実測値で比較しろと>俺。
それはさておき!
1.65kHzから上に多数のピークが見えます。(分割振動や共鳴が発生しているものと思われます)
それとなく【グラフ1】の音圧ピークとの関係が見て取れるようにも思います。
個人的に気になります点としては、
左右チャンネルで1.6kHzから上のピークの周波数のズレが大きいように見えますから、
高域の左右バランスが周波数によってフラフラする感じは比較的強めかもしれませぬ。
いや、気にするほどでもないかもしれませんけれど。
=============================================
過渡応答も比較してみました。(2010/10/24追加)
せっかくだから、手持ちのeditionシリーズも測定いたしました。(測定方法はココ)
おっ母・・・edition7のパッド、まだカビてなかったよ
| |
|
インパルス応答 |
ステップ応答 |
位相(音響)※灰色の線が位相です。 |
|
LoopBack
(この測定系での理想応答) |
|
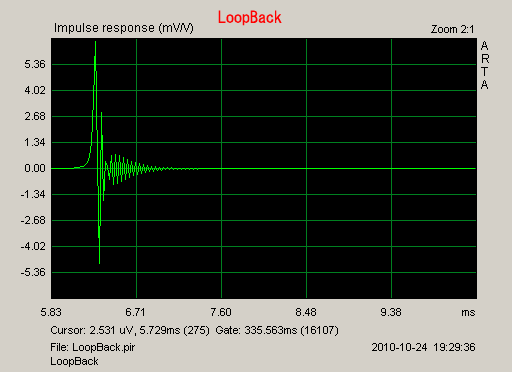
自分の測定系(再生+録音)では若干高域の位相遅れがあり、こんな感じになってます。
→位相(音響)グラフを参照 |
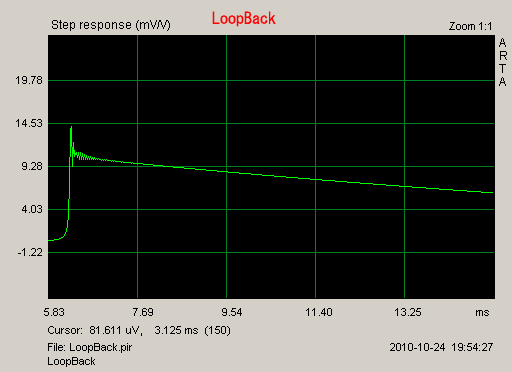
ステップ応答はインパルス応答を積分したものです。
ということは、インパルス応答はステップ応答を微分したものですよ、奥さん。 |
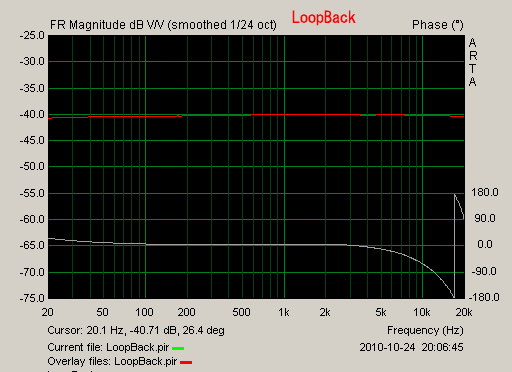
高域で位相が遅れていますが(´・ω・`) 、これは主にFA-66の特性によるものです。
(プリエコーを排除するためにこのような設計にしているのかも知れません。憶測ですけど。)
振幅については、0.5dB程度ローエンドとハイエンドに音圧の落ち込みあり。この程度はご勘弁。 |
|
HD650
<参考> |
|
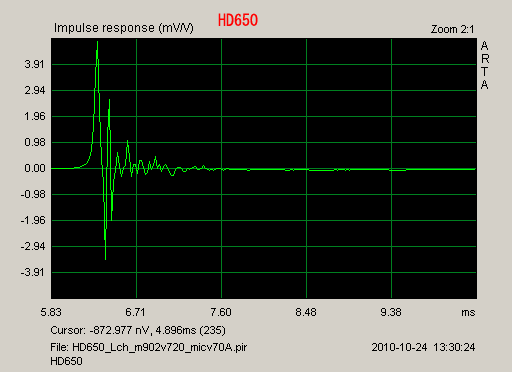 |
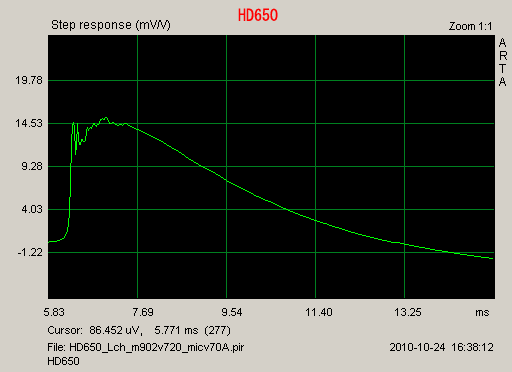 HD650は低音に僅かに遅れがある以外は綺麗なもんです。 HD650は低音に僅かに遅れがある以外は綺麗なもんです。 |
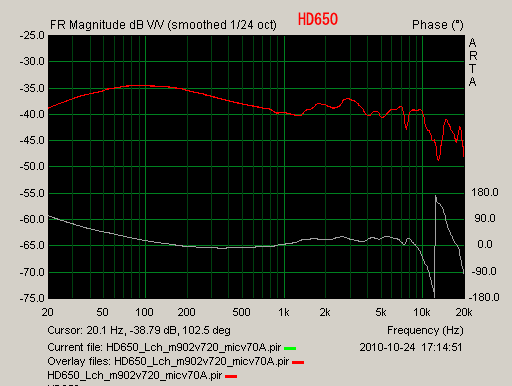 |
|
| edition10 |
|
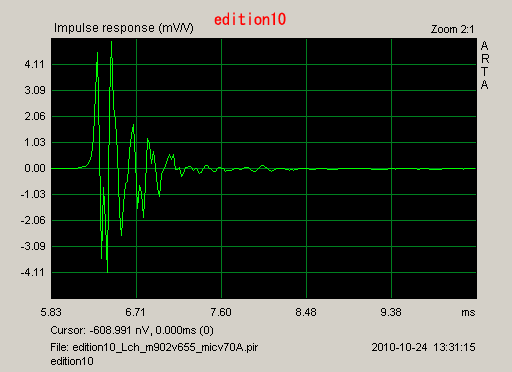 |
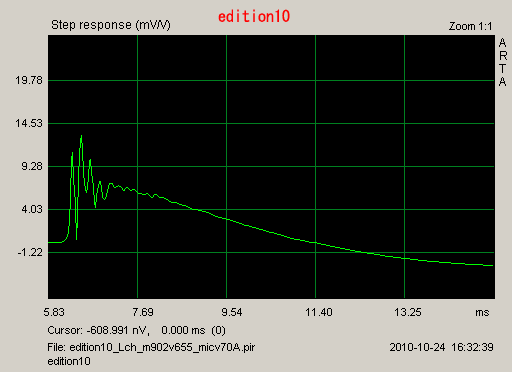 立ち上がり部分の応答が特によろしくありません。 立ち上がり部分の応答が特によろしくありません。 |
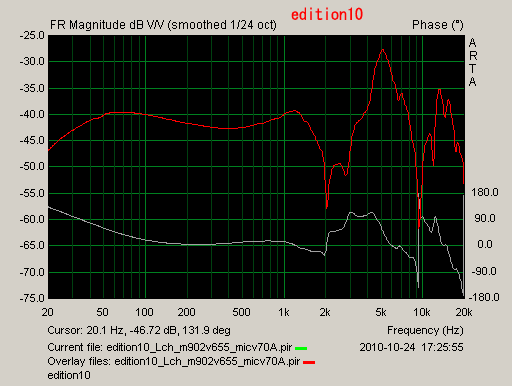 |
|
| edition9 |
|
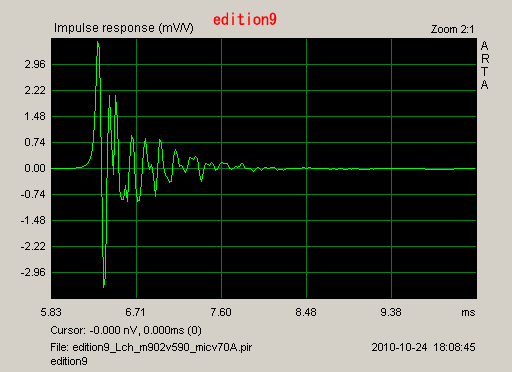 |
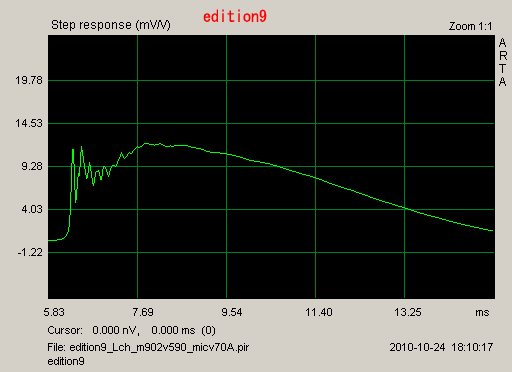 |
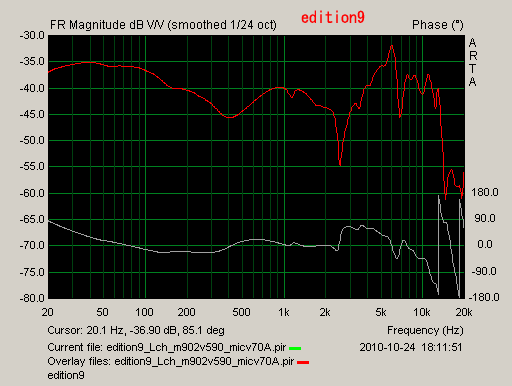 |
|
| edition8 |
|
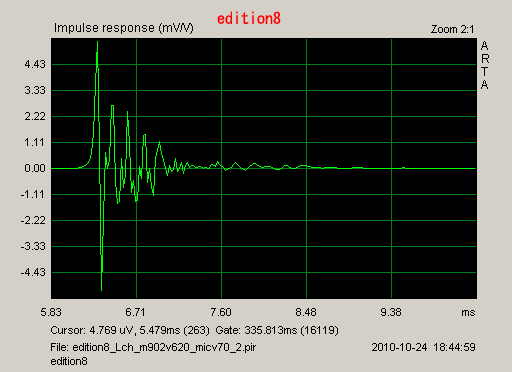 |
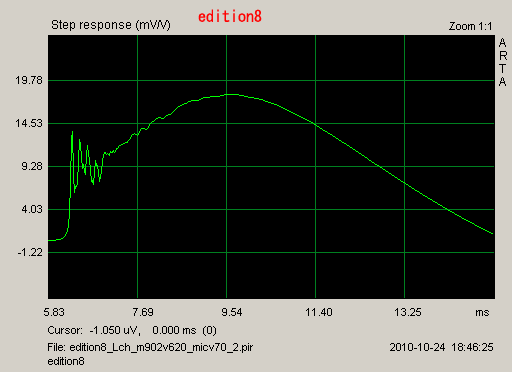 低音が遅れてボヨーンとしておる様子あり。 低音が遅れてボヨーンとしておる様子あり。 |
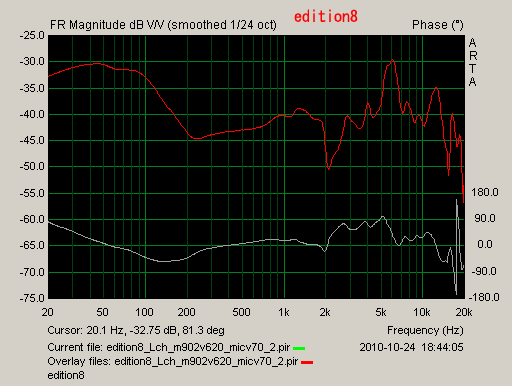 |
|
| edition7 |
|
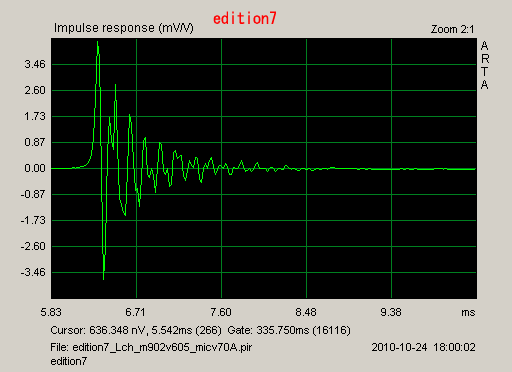 |
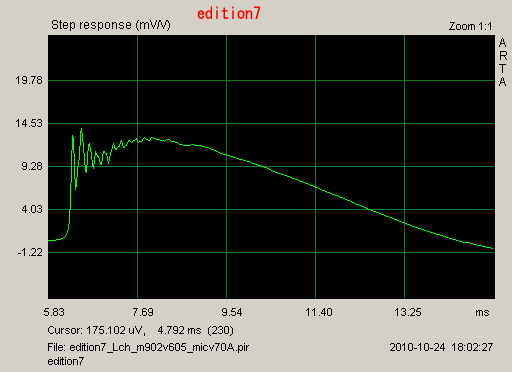 edition9と似てますそっくりですあたりまえです。 edition9と似てますそっくりですあたりまえです。 |
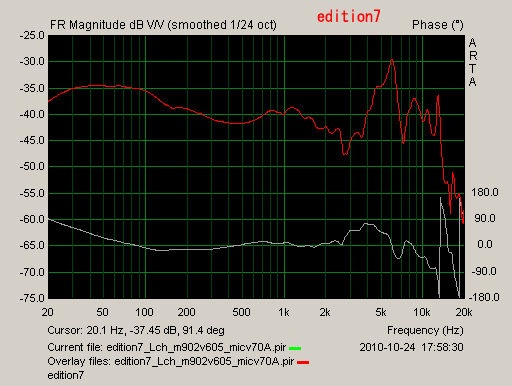
僅かにedition7の方が、400Hzあたりがフラットのように見えなくもないですが、
まあ個体差程度かもしれません。 |
ご参考のため、自分の測定系について書いておきます。
【俺測定系(オーバーヘッド編)】
タイトルページの下の方にも概要を書いてますが、
オーバーヘッドの場合の、おいらの 測定系は毎度のごとく以下のとおり、
・刺激信号再生:ARTA1.61(48kHzサンプリング LogChirp信号) >(SPDIF)> m902 > 測定対象ヘッドホン
・刺激応答録音:バイノーラルマイクSP-TFB-2(俺頭装着) > EDIROL FA-66 > ARTA1.61
また、インパルス応答はARTAにて算出していますが、その方法は、
入力信号のLogChirp信号と、刺激応答とをコンボリューション(畳み込み)してインパルス応答を得ています。
(ARTAでは、刺激信号として、MLS、リニアスイープ、ホワイト/ピンクノイズ、外部刺激信号も扱えます。)
最近の音響測定ソフトでインパルス応答を求める場合は、S/N向上やルームアコースティックを排除する観点から、
刺激信号として擬似パルスではなく、LogChirp信号やMLS信号といった、スペクトルをまんべんなく含んだ信号を使うことが多いのです。 |
TOPへ戻る
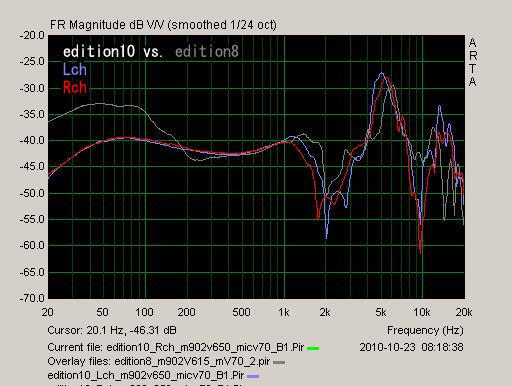
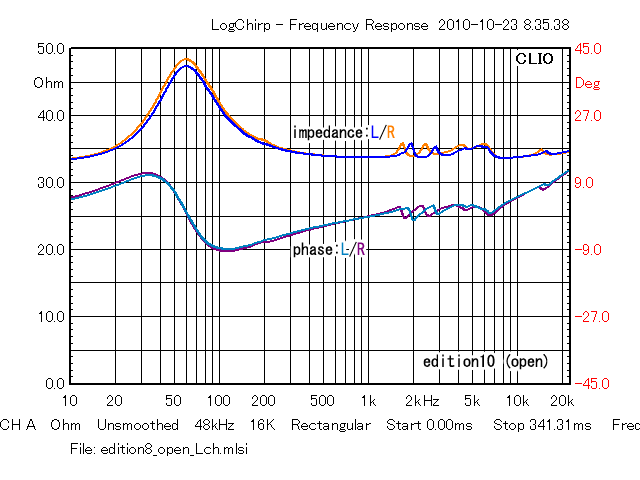
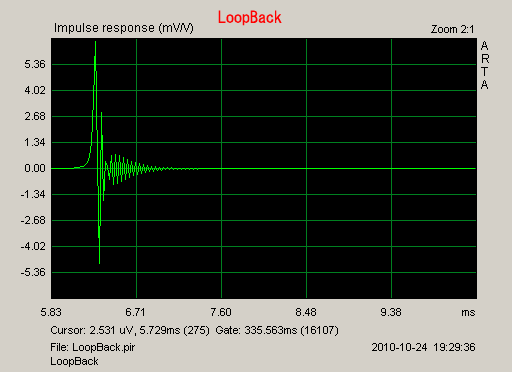
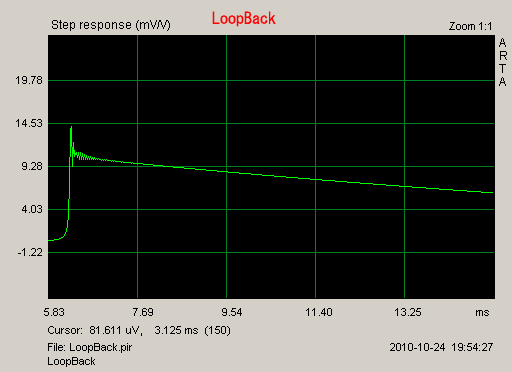
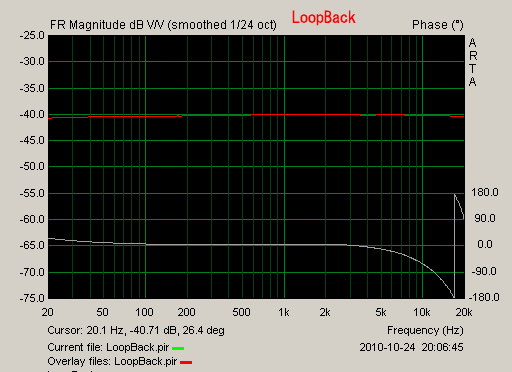
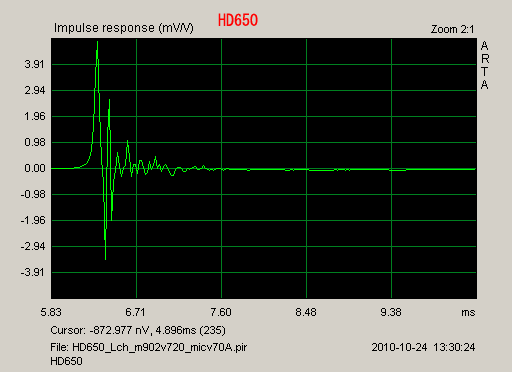
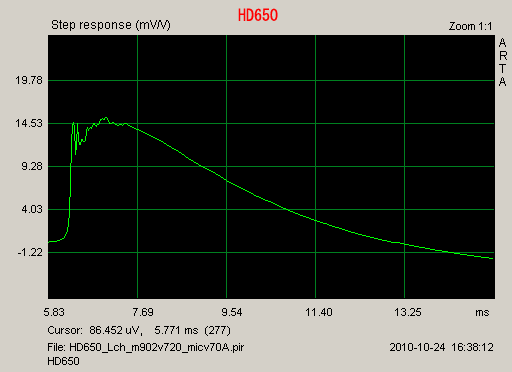 HD650は低音に僅かに遅れがある以外は綺麗なもんです。
HD650は低音に僅かに遅れがある以外は綺麗なもんです。 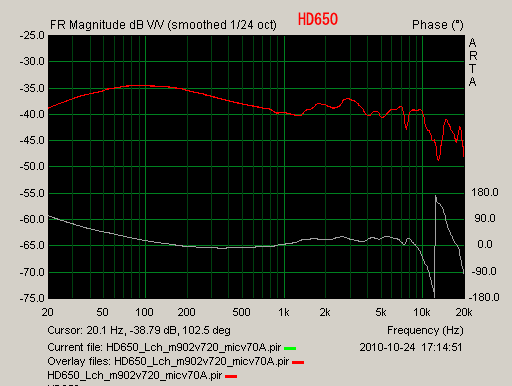
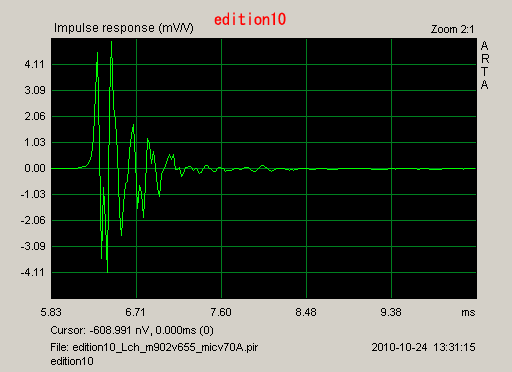
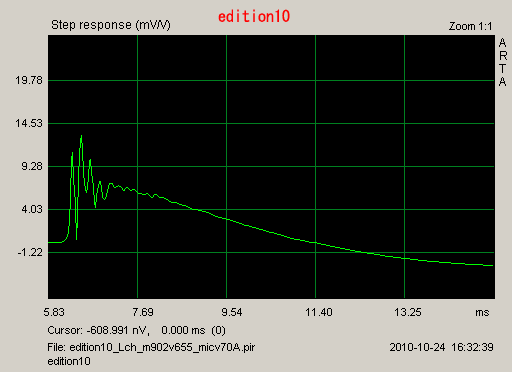 立ち上がり部分の応答が特によろしくありません。
立ち上がり部分の応答が特によろしくありません。 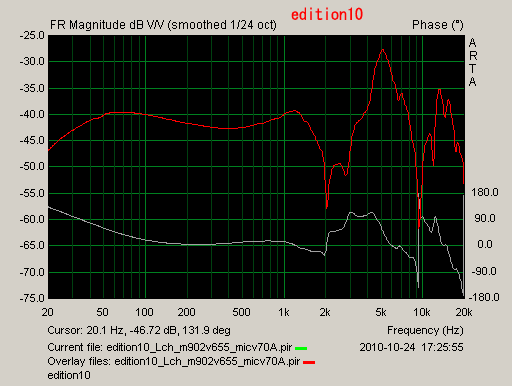
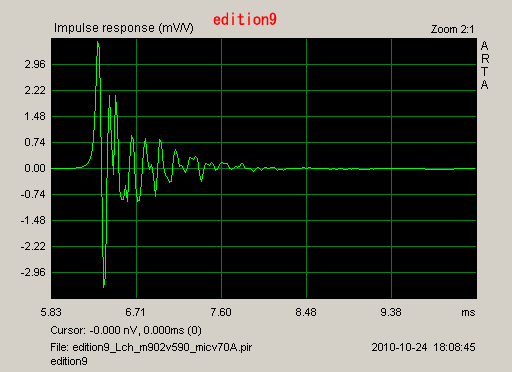
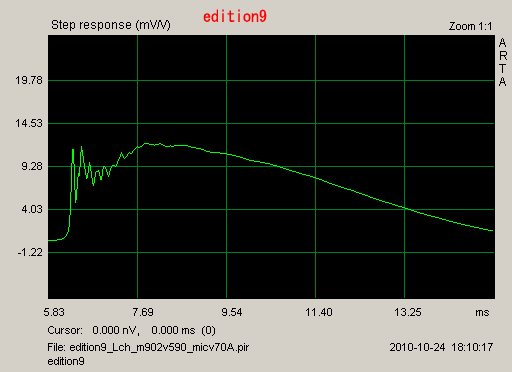
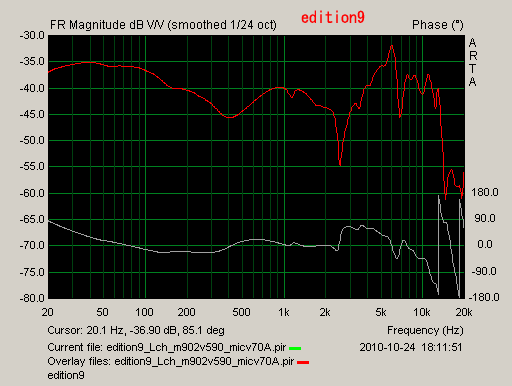
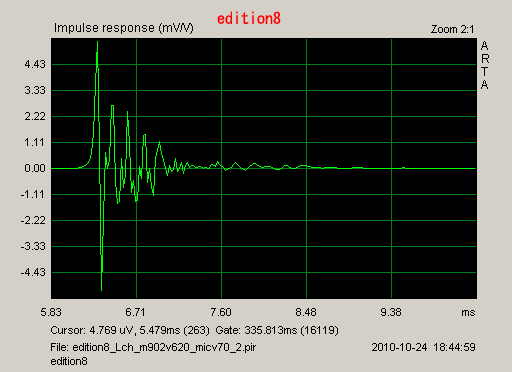
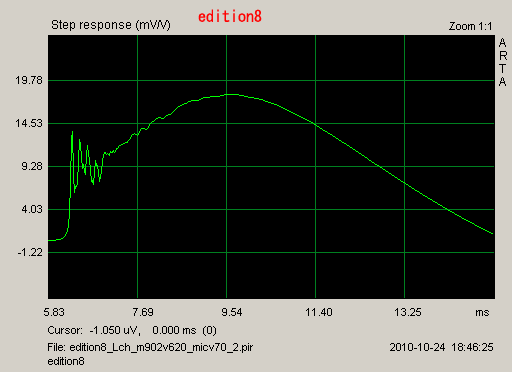 低音が遅れてボヨーンとしておる様子あり。
低音が遅れてボヨーンとしておる様子あり。 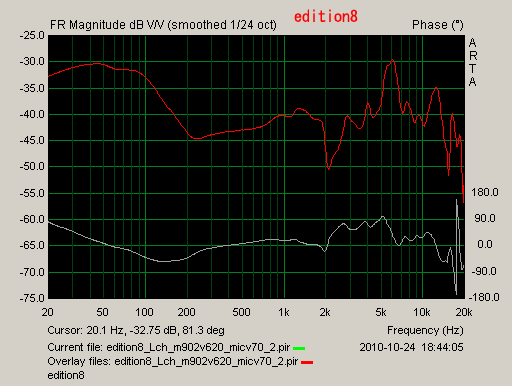
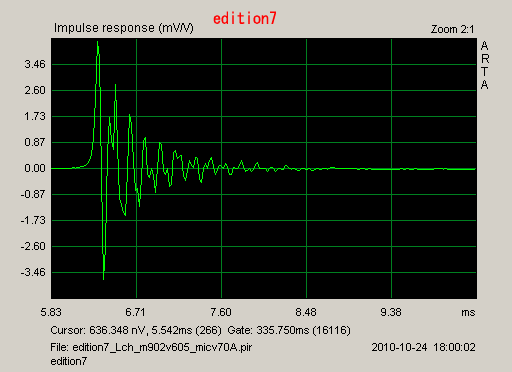
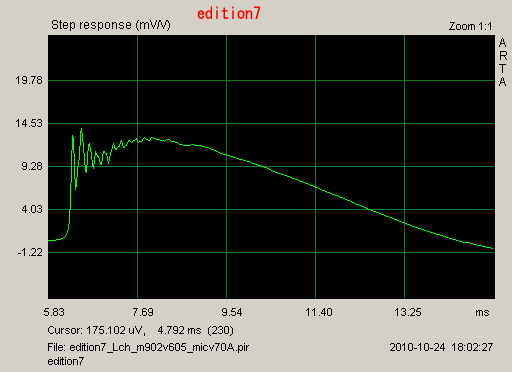 edition9と似てますそっくりですあたりまえです。
edition9と似てますそっくりですあたりまえです。